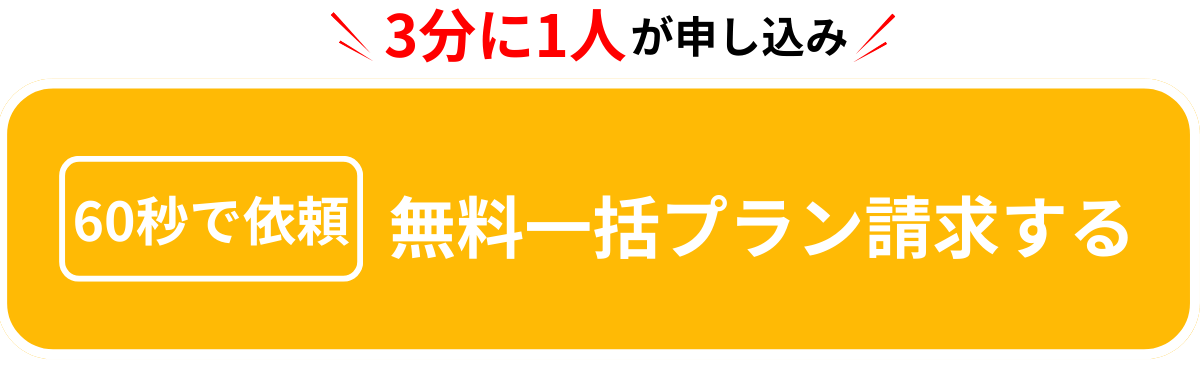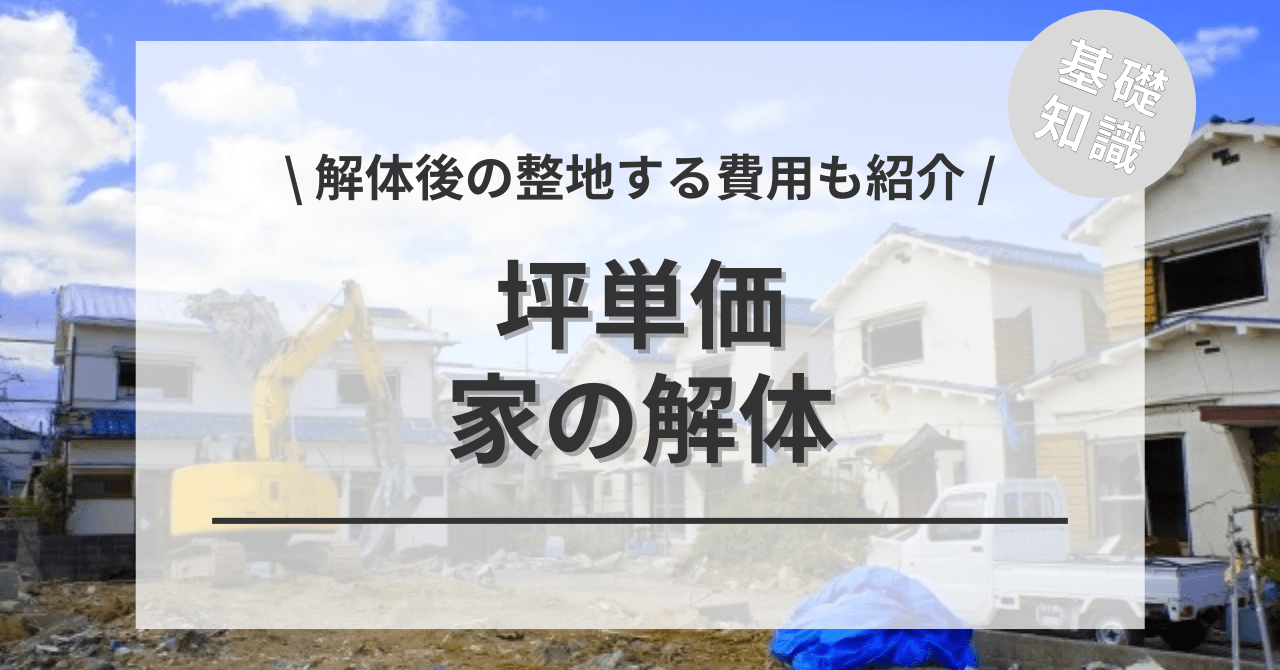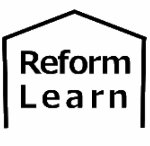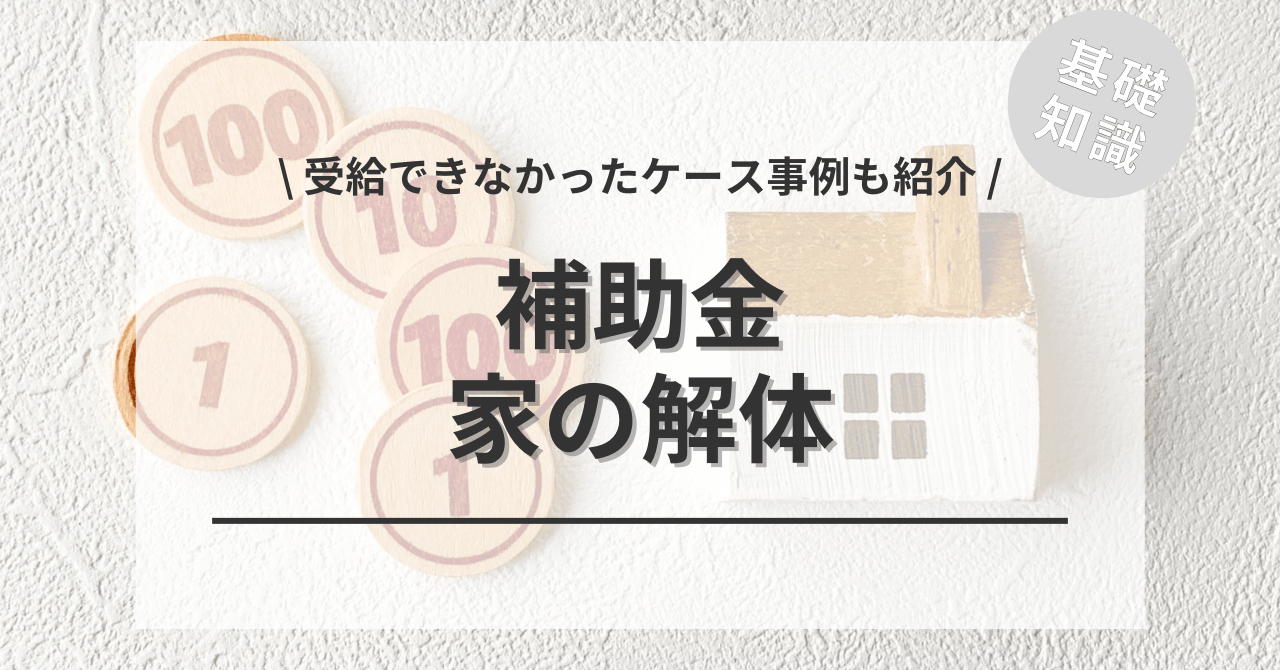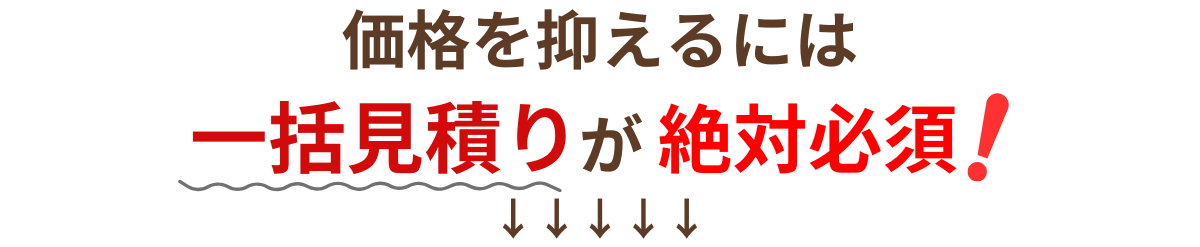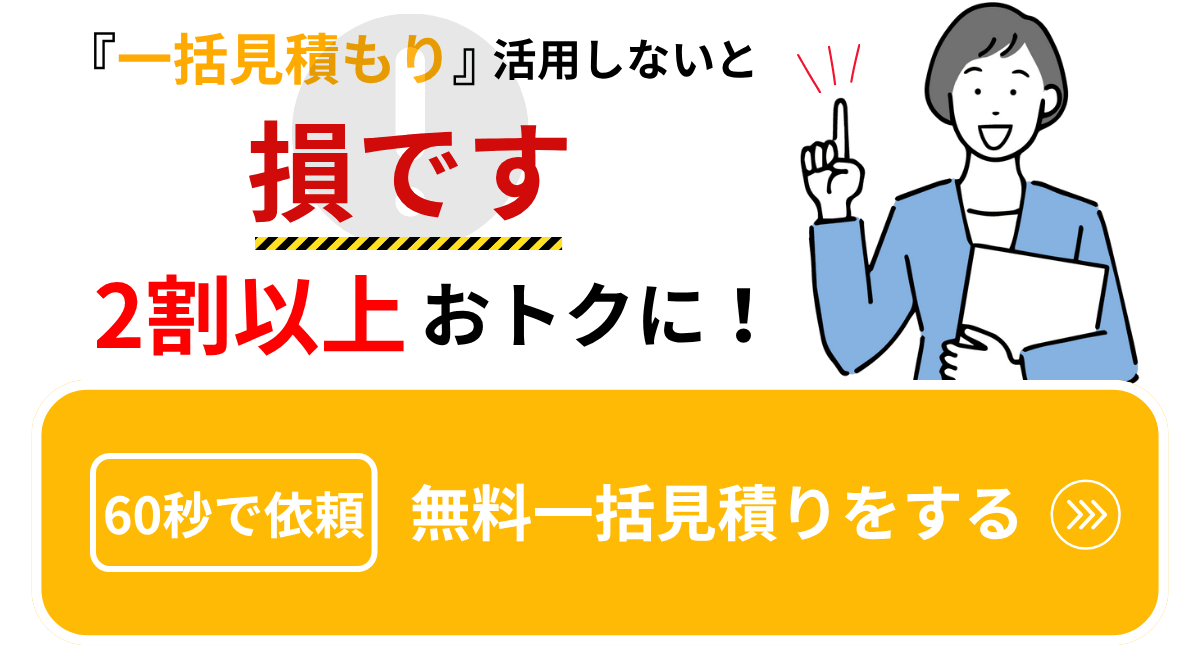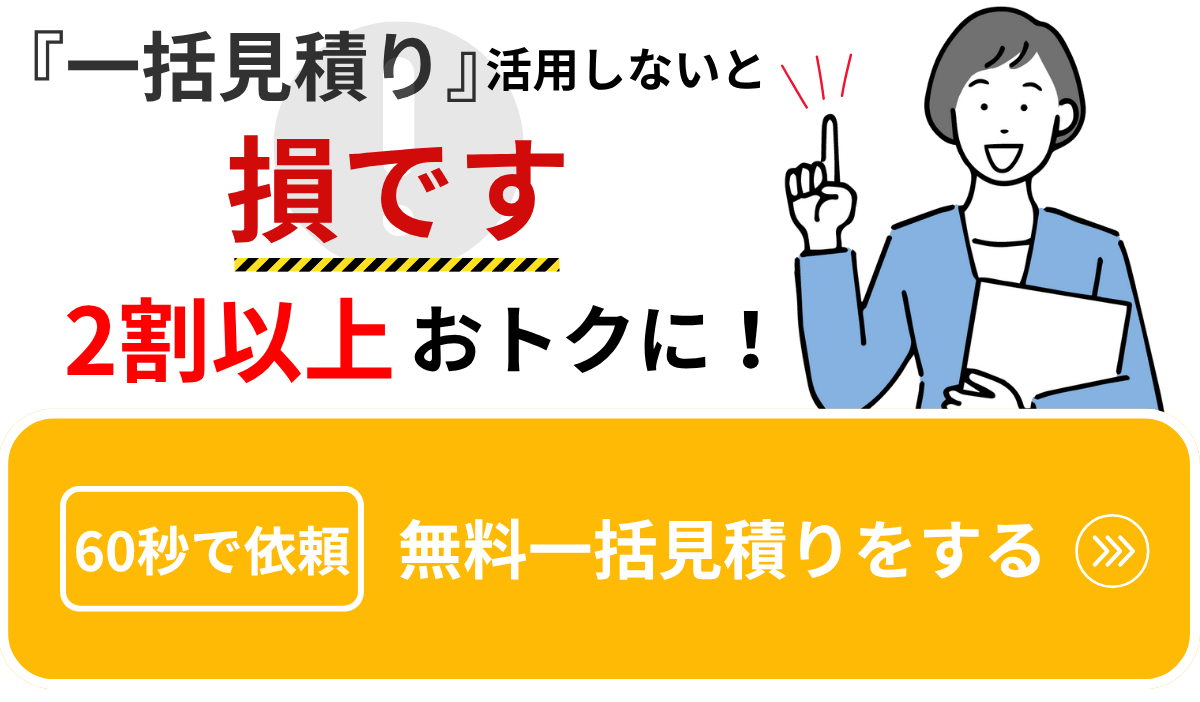家の解体費用の補助金の相場

解体費用の補助金=
100,000円〜2,000,000円
家の解体費用の補助金ですが、各地方自治体の総合した平均の補助金額となります。下の方に詳細を載せてありますのでご確認下さい。また、この相場は一例となっております。正確な金額は各自治体に事前確認しましょう。
家の解体費用の補助金とは?

解体費用は数百万円に及ぶこともあり、個人負担が大きいのが現実です。そこで、多くの市区町村では「空き家対策事業」の一環として補助金を支給しています。補助金は申請すれば必ず受けられるものではなく、自治体の要件を満たした家屋が対象となります。代表的な対象は、老朽化が進み「危険家屋」に該当する建物や、1年以上居住していない空き家などです。
支給額の相場
支給される金額は地域によって差がありますが、一般的には10万円~200万円程度が相場です。ある地域では「工事費用の○割(上限金額あり)」という方式をとり、別の地域では「定額補助」として金額を明示している場合もあります。
| 自治体方式 | 特徴 | 相場金額 |
|---|---|---|
| 定額支給型 | 一律で決められた金額を支給(例:上限100万円) | 約10万~100万円 |
| 割合支給型 | 解体費用の○割を負担(例:費用の1/3まで、上限150万円) | 約30万~200万円 |
| 加算方式 | 老朽危険家屋など特定条件に応じて加算あり | 条件によって増額 |
補助金の正式名称と種類
自治体によって制度の名前は異なります。代表的なものには以下のような呼び方があります。
| 名称の一例 | 特徴 |
|---|---|
| 空き家解体補助金 | 空き家対策の中心制度。放置空き家を対象とするケースが多い。 |
| 老朽家屋等解体工事助成 | 老朽化や危険性が認められた建物に限定。 |
| 危険廃屋解体撤去補助金 | 倒壊の危険性が高い家屋の撤去を目的とする。 |
| 解体撤去費助成 | 個人所有の空き家の一般的な解体費に対して支給。 |
補助金を受けるための要件
補助金を受けるには、申請前に要件を満たしているかを確認する必要があります。代表的な条件は次の通りです。
1年以上居住していないこと(空き家として認定される必要あり)
住宅以外の用途で活用していないこと
一戸建て住宅または併用住宅であること(共同住宅は対象外のことが多い)
これらはあくまで一例であり、実際には自治体ごとに細かな基準が異なります。そのため、申請前に役所や自治体の公式サイトで必ず確認することが重要です。
【主要都市の解体補助金・助成金 一覧】
| 自治体名 | 制度名 / 内容 | 補助率・補助額上限 | 主な条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 | 対策地区:戸建て住宅上限75万円/棟、集合住宅150万円/棟。重点対策地区では戸建て100万円、集合住宅200万円。補助率は「解体および整地費用」と「大阪市の定め額」の低い方の1/2以内(対策地区)、2/3以内(重点対策地区)。 | 対象建物は、狭あい道路に面する敷地(道路幅等の条件あり)、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅など。 |
| 大阪府 門真市 | 危険家屋等除却補助 | 一戸建て住宅:解体工事費用の4/5、上限60万円。長屋または共同住宅の場合、戸当たり30万円で、棟としては上限200万円。 | 建物が老朽化かつ空き家、昭和56年5月31日以前建築など。市の要件を満たすこと。 |
| 東京都 | 空き家家財整理・解体促進事業 | 解体に係る費用(消費税等除く額)の1/2、上限10万円。 | 東京全域の空き家が対象。補助はあくまで「解体促進」のための制度。申請要件あり。 |
| 東京都 新宿区 | 老朽危険空家除却助成 | 工事費の2/3を補助、上限80万円。 | 対象は昭和56年5月以前建築の木造住宅など。老朽化・危険性が認められること。 |
| 東京都 墨田区 | 老朽危険家屋除却費助成 | 上限50万円、工事費の1/2。 | 倒壊の危険性が認められる住宅。一定の構造・建築年次などが条件。 |
| 東京都 世田谷区 | 不燃化特区制度(老朽建築物除却等) | 上限200万円。 | 一定の「不燃化特区」に指定されている地域で、老朽建築物の解体・除却が対象。条件・区域が限られる。 |
自治体の補助金を上手に活用すれば、解体費用の大きな負担を軽減し、次の土地活用や理想の家づくりにスムーズにつなげることができます。
解体補助金を給付してもらう流れ
家の解体には数十万円から数百万円の費用がかかることも多く、経済的な負担は決して小さくありません。そのため、多くの自治体では「空き家対策」や「防災・安全確保」を目的として、解体費用の一部を補助する制度を設けています。ただし、補助金を受けるためには決められた手続きを踏む必要があり、申請から給付までには一定の流れがあります。ここでは、解体補助金を受け取るまでの一般的なステップをわかりやすく解説します。
1. 事前確認・情報収集
まずは、自分の住んでいる市区町村に解体補助金制度があるかどうかを確認します。自治体の公式ホームページや役所の建築課・都市整備課などで情報が公開されています。対象条件(築年数・空き家の有無・危険性の有無など)を確認し、制度を利用できるか検討します。
2. 相談・申請書類の入手
補助金制度の対象になりそうであれば、自治体の窓口に相談に行きます。その際、必要な申請書類や添付書類(登記簿謄本、建物の写真、固定資産税の納税証明書など)を案内してもらえます。
3. 補助金交付申請
解体工事を始める前に、補助金の申請を行います。申請は必ず工事前に行うことが必須で、事後申請は認められません。申請後は自治体による審査・現地確認が行われ、対象建物かどうかが判断されます。
4. 補助金交付決定通知
審査を通過すると、自治体から「交付決定通知」が届きます。これを受け取ってから、解体業者に正式発注し工事を進めることができます。交付決定前に解体を始めてしまうと、補助金の対象外になるので注意が必要です。
5. 解体工事の実施
解体工事を実際に行います。工事の様子を記録するために、工事中や完了後の写真を撮影しておく必要があります。業者には補助金利用の旨を伝えておくとスムーズです。
6. 実績報告書の提出
工事完了後、業者から受け取った「請求書」「領収書」などを添付して、自治体に実績報告書を提出します。この報告をもとに、補助金の最終審査が行われます。
7. 補助金の確定・給付
自治体で報告内容と工事内容が確認されると、補助金の交付が確定します。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
家の解体補助金を利用する際の注意点
家の解体補助金は、費用負担を大きく減らせる魅力的な制度ですが、申請から給付までには多くの条件や制約があります。正しく理解して手続きを進めなければ、「補助が受けられなかった」という結果にもなりかねません。ここでは、補助金を申請する際に特に注意すべきポイントをまとめます。
1. 工事前に申請が必要
解体工事を始めてから補助金を申請しても、原則として認められません。必ず工事前に補助金の交付申請を行い、交付決定通知を受け取ってから着工することが必要です。
2. 対象条件を満たしていないと不可
補助金はすべての家が対象ではありません。主な条件としては以下があります。
1年以上空き家であること
個人所有であること(法人所有は対象外のケースが多い)
一戸建て住宅または併用住宅であること
自治体ごとに基準は異なるため、自分の家が条件に該当するか必ず確認しましょう。
3. 補助金額には上限がある
補助金は解体費用をすべて負担してくれるわけではありません。多くの自治体では「工事費用の○割、上限○○万円」という形で支給されます。例えば、費用が200万円かかっても、上限が100万円であればそれ以上は自己負担となります。
4. 書類不備で不交付になる可能性
申請時や実績報告時には、登記簿謄本・固定資産税証明書・工事前後の写真・領収書など、多数の書類が必要です。書類不備や提出遅れがあると、補助金が受けられないケースもあるので注意が必要です。
5. 予算枠に限りがある
自治体の補助金には予算枠があり、先着順や年度内の枠が埋まると受付終了になることがあります。年度初めに申請を開始するケースが多いため、早めに確認・申請することが重要です。
6. 補助金の給付までに時間がかかる
補助金は申請後すぐに支給されるわけではありません。工事完了後に実績報告を提出し、審査を経てから給付されます。そのため、実際にお金が振り込まれるまで数週間から数か月かかることを想定しておきましょう。
7. 工事業者の選定にも注意
補助金を利用する場合、登録された業者や一定の資格を持つ業者に依頼しなければならない自治体もあります。安さだけで業者を決めず、補助金の要件に合うかどうかも確認が必要です。
解体工事を業者に依頼し、工事が始まってから「補助金がある」と知って申請したが、工事前の申請が必須だったため対象外となったケース。
空き家として認められなかった
実際には年に数回使用していたため「完全な空き家」とみなされず、要件を満たさないとして却下されたケース。自治体によっては「1年以上誰も住んでいないこと」が条件になるため、短期間でも使用履歴があると対象外になることがあります。
書類不備や期限切れ
登記簿謄本や写真、領収書の添付漏れがあり、修正提出の猶予期間を過ぎてしまい不交付になったケース。特に工事前後の写真は必須なのに撮影忘れで却下される事例が多いです。
法人名義の家だった
個人ではなく会社名義の物件を解体したため、制度対象外とされてしまったケース。多くの自治体は個人所有の住宅が対象条件になっています。
予算枠が終了していた
年度末に申請したところ、すでに自治体の補助金予算が上限に達しており受付終了となったケース。人気の地域では特に起こりやすいです。
【申請をスムーズに進めるコツ】
補助金は年度予算で動いており、早い者勝ちの要素が強いです。年度初め(4月以降)に早めに確認することでチャンスを逃しにくくなります。
必要書類を事前に揃える
登記簿謄本・固定資産税証明書・工事見積書・工事前の現地写真などは事前に揃えておくと申請がスムーズ。特に写真撮影は忘れるとやり直しができないため注意が必要です。
業者選びは「補助金対応実績あり」を優先
解体業者の中には補助金制度に詳しい会社も多く、書類の準備や自治体とのやり取りをサポートしてくれることがあります。初めての方は補助金対応実績のある業者を選ぶのがおすすめです。
申請内容は正直に書く
「実際には住んでいるが空き家扱いにして補助金をもらう」などの虚偽申請は発覚すると不正受給の返還請求につながります。正直に申請し、必要であれば自治体担当者に相談しましょう。
解体後の活用計画も考えておく
自治体によっては、解体後に「更地を駐車場として貸し出す」など有効活用する計画があると優遇されるケースもあります。補助金をきっかけに土地活用の方向性も整理しておくと良いでしょう。
家の解体費用を補助金以外で安くする方法は?

家の解体費用を補助金以外で安くする方法には、相見積もりを取り、業者の費用を比較することです。
家の解体を依頼できる業者は、ハウスメーカー・工務店・個人業者・建築事務所など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。
相見積もりとは?
相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。
解体費用を安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用で家の解体を行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。
一括見積もり無料サービスで安く家の解体をできる優良業者を探す!
一括見積もり無料サービスとは、家の解体を得意としている優良会社の見積もりを複数社一括で行う無料サービスです。また、お客様自身で気になる会社や業者を選ぶことができ安心して費用や会社を比較や検討することができます。
『全てがわかる!』
家の解体の費用に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:家の解体の費用の相場は?