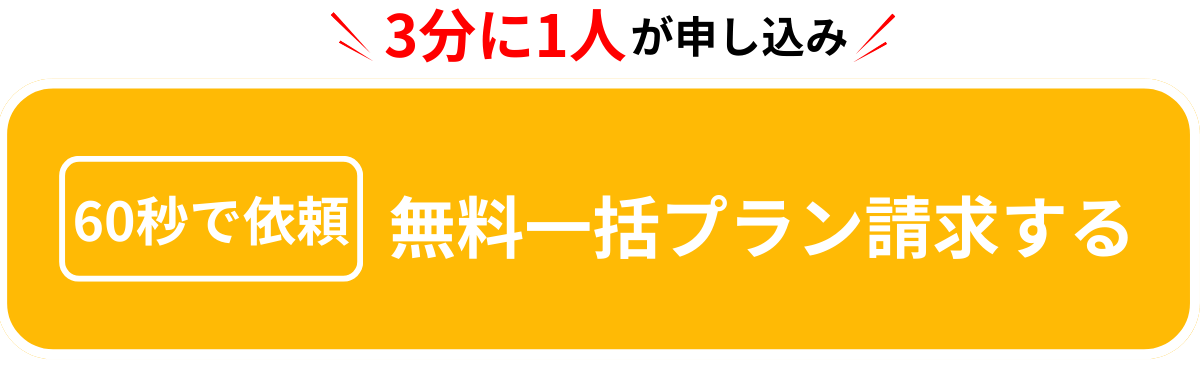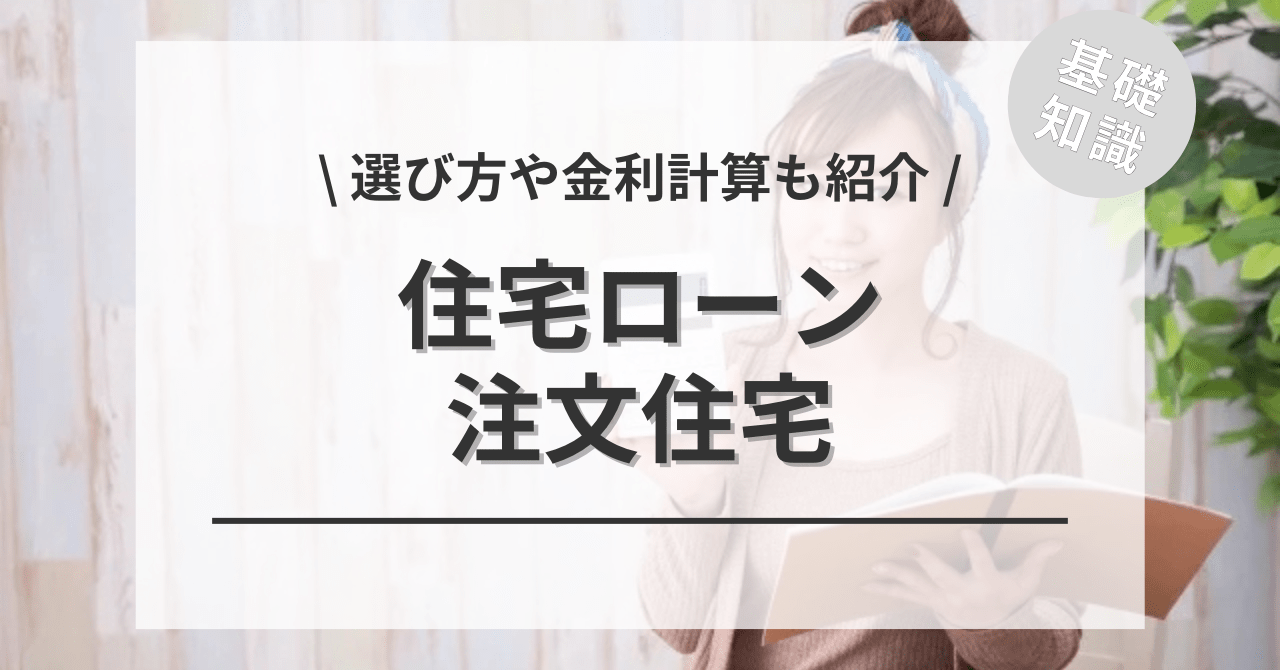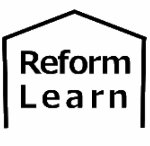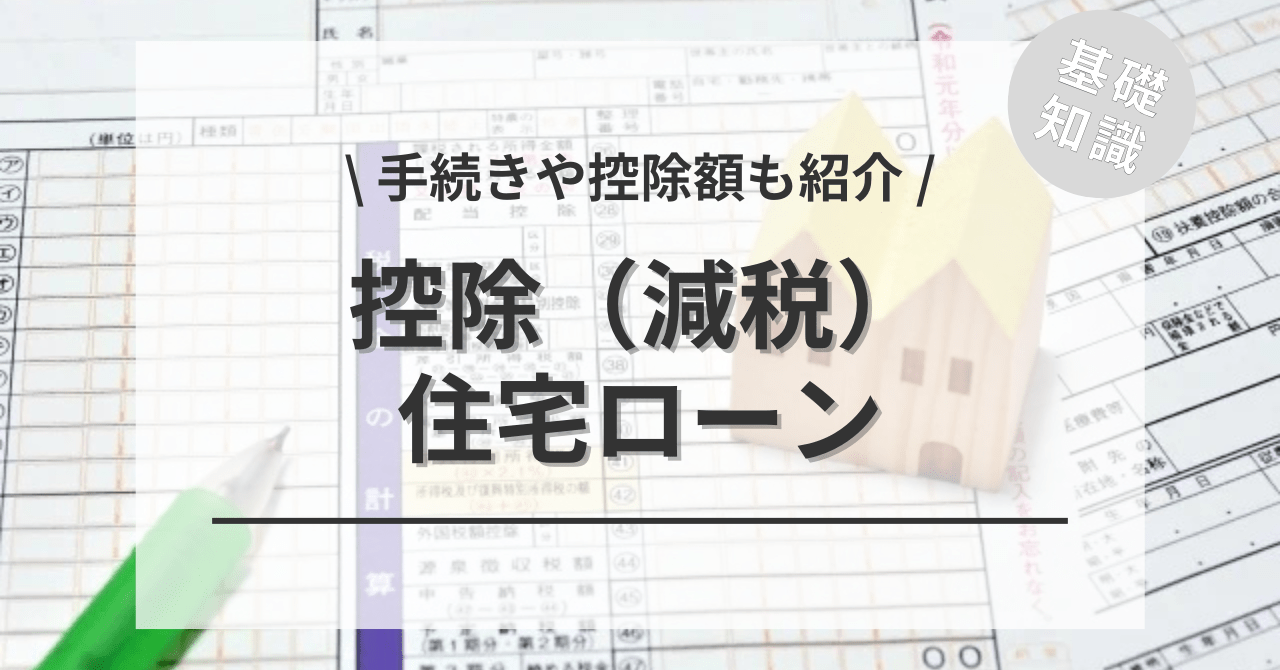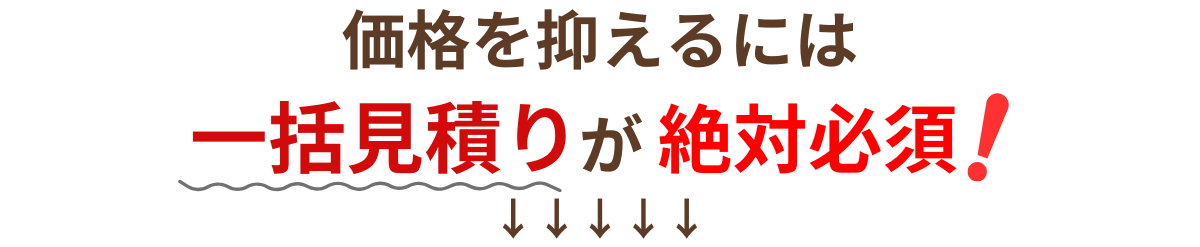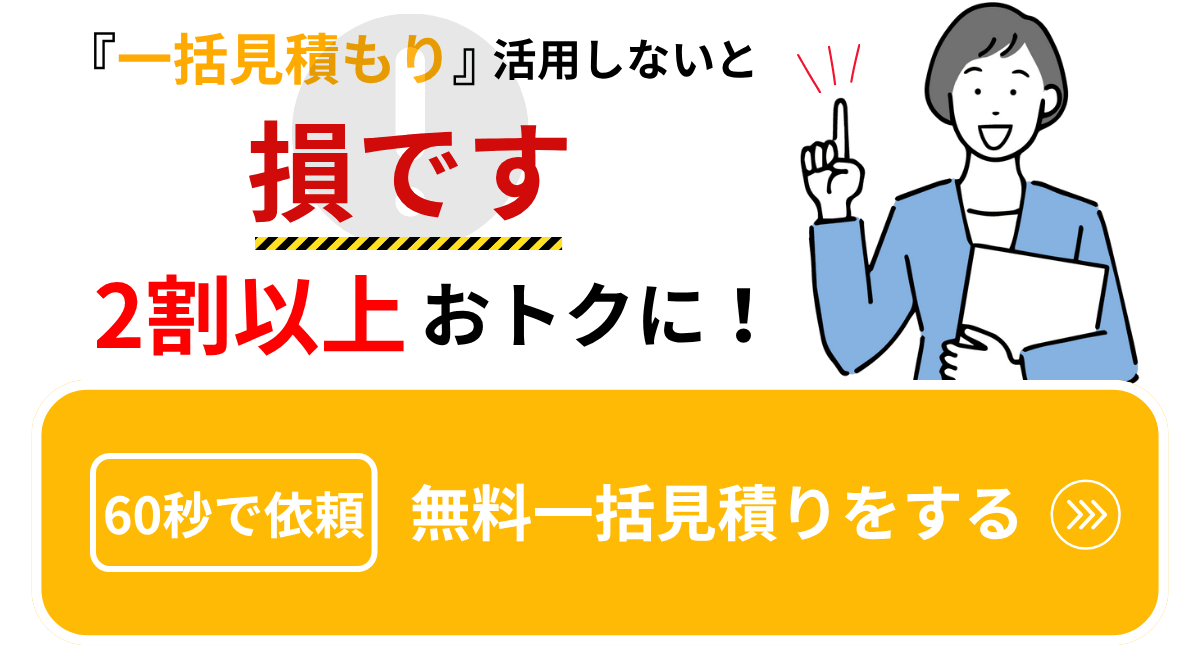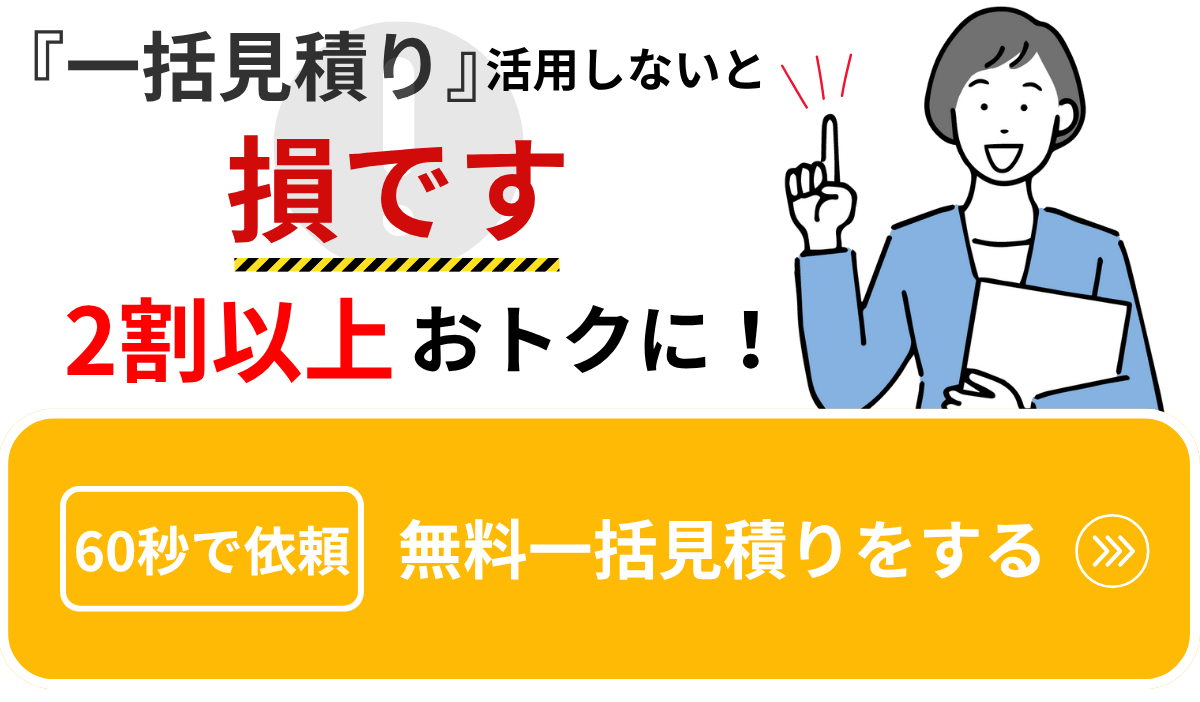住宅ローン控除(減税)とは?

住宅を購入する際、多くの人は住宅ローンを利用しますが、その負担を軽減するために国が設けている税制優遇制度が「住宅ローン控除(減税)」です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、一定の条件を満たす住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、毎年支払う所得税や住民税の一部が控除される仕組みとなっています。
制度の目的
住宅ローン控除の大きな目的は、住宅を購入する人の経済的負担を軽減し、安定した住環境の整備を促進することです。特に住宅は人生で最も大きな買い物のひとつであり、ローンによる長期的な返済が大きな負担となります。控除制度を設けることで、その負担を和らげ、より多くの人が安心してマイホームを取得できるよう支援しているのです。
仕組みと内容
住宅ローン控除では、年末時点の住宅ローン残高に対して一定割合(通常は1%)を計算し、その金額が所得税から差し引かれます。例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、1%にあたる30万円が控除額となり、所得税がその分軽減されます。もし所得税額が控除額を下回る場合は、住民税からも一部が控除される仕組みです。
この控除は原則として10年間、条件を満たす場合には最長13年間まで受けられるケースもあり、長期にわたって家計の支えとなります。
適用される住宅の種類
住宅ローン控除は、新築住宅だけでなく、中古住宅やリフォームにも条件を満たせば適用される場合があります。例えば、省エネ基準を満たす住宅や、一定の床面積以上の住居などが対象です。ただし、投資用やセカンドハウスなどは対象外となるため注意が必要です。
住宅ローンの控除を受ける「手続き」は?

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームした人にとって非常に大きな節税メリットがあります。ただし、控除を受けるためには自動的に適用されるわけではなく、必ず「確定申告」を行い、必要な手続きを経ることが求められます。特に初年度は、税務署に必要書類を提出することが条件となるため、事前にしっかり準備しておくことが大切です。
確定申告による手続きの流れ
住宅ローン控除を受けるには、まず税務署で確定申告を行う必要があります。確定申告は毎年2月中旬から3月中旬にかけて受け付けられ、初年度に申請を行えば、2年目以降は勤務先での年末調整で控除を受けられるケースが一般的です。
初年度の申請では、以下の必要書類を提出することが必須となります。
確定申告で必要となる書類一覧
住宅ローン控除を受けるためには、以下の書類を用意する必要があります。書類は金融機関や市区町村、勤務先など複数の場所から集めることになるため、早めの準備が安心です。
控除額を算出するための書類で、確定申告の際に必ず添付が必要です。
住民票の写し
購入した住宅に実際に居住していることを証明するために必要です。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
金融機関から送付される書類で、住宅ローン残高を証明するためのものです。
家屋に関する証明書類(登記事項証明書・請負契約書の写しなど)
住宅の床面積や増改築の年月日、費用の額を証明するために必要です。
建築確認済証・検査済証または増改築等工事証明書
建築基準法を満たしているかどうかを確認するための証明書です。
給与所得者の場合:源泉徴収票
勤務先から交付される書類で、所得額や既に納付した税金額を確認するために提出します。
住宅ローン控除は節税効果が大きいため、しっかりと手続きを行い、その恩恵を最大限に活用しましょう。
住宅ローンの控除額は?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅を購入した際のローン残高に応じて、所得税や住民税から一定額を差し引いてもらえる制度です。返済の負担を軽減し、安心して住宅を取得できるように設けられた仕組みであり、マイホームを検討する人にとって大きなメリットとなります。控除額は住宅ローンの残高や所得額によって変動するため、自分がどの程度の恩恵を受けられるかを事前に理解しておくことが大切です。
控除額の基本的な仕組み
住宅ローン控除額は「年末時点の住宅ローン残高の1%」が基準となり、その金額が所得税から差し引かれます。例えば、年末のローン残高が3,000万円であれば、その1%にあたる30万円が控除対象となります。この控除は原則として10年間継続して受けることができ、長期にわたって家計の負担を軽減してくれます。
ただし、控除されるのは実際に支払う税額までが上限であり、所得税が少ない場合や住民税の額が小さい場合には、最大額の控除を受けられないケースもあります。
最大控除額を受け取るための条件
「最大控除額」を必ずしも全員が受けられるわけではありません。控除をフルに受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
所得税と住民税を合わせて年間40万円以上の税額があること
つまり、住宅ローン残高が多くても、支払う税額が少なければ控除を受けきれないケースがあります。反対に、所得税額や住民税額が十分にあり、かつ年末残高が条件を満たしていれば、最大で年間40万円の控除が適用され、10年間で合計400万円もの節税効果を得ることができます。
控除額が変動するケース
住宅ローン控除額は、年末残高や税額に左右されるため、人によって実際の控除額は異なります。例えば以下のようなケースでは控除額が変わります。
ローン残高が少ない場合 → 年末残高が低ければ、その1%の額が小さくなり控除額も少なくなる。
借入から10年以上経過した場合 → 控除は原則10年間のみであり、それ以降は適用されない。
マイホーム購入を検討する際には、自分の所得額やローン残高を踏まえてどの程度の控除が見込めるのかをシミュレーションし、将来の家計に与える効果を確認しておくことが重要です。
住宅ローン控除の対象となる「住宅ローン」とは?
住宅ローン控除を受けるためには、どんなローンでも対象になるわけではありません。国の制度である以上、一定の条件を満たした住宅ローンのみが控除の対象となります。民間の銀行ローンだけでなく、公的機関や勤務先からの融資なども対象となりますが、その内容には細かいルールがあります。ここでは、住宅ローン控除の対象となるローンの種類と、その条件について詳しく解説します。
対象となる住宅ローンの種類
住宅ローン控除の対象となるのは、以下のような金融機関や制度を通じて借り入れた住宅ローンです。
地方自治体による融資
財形住宅融資(勤務先を通じた財形貯蓄を利用したローン)
長期固定金利ローン「フラット35」(住宅金融支援機構と民間金融機関の提携商品)
勤務先からの融資(年利0.2%以上のものに限る)
これらはすべて、住宅取得を目的とした正式な融資であることが前提です。
対象外となる住宅ローンの例
一方で、以下のような借入は住宅ローン控除の対象外となります。
前所有者のローンを引き継いだ借入れ
支払時期や返済条件が不明確な融資
このようなケースは「公的に証明できる融資」とは見なされず、控除の対象から外れるので注意が必要です。
勤務先からの借入れにおける条件
勤務先から住宅ローンを借りる場合でも、控除対象となるには条件があります。
利子補給制度(勤務先が利息の一部を負担する制度)がある場合は、補給後の実質金利が年0.2%以上であること
つまり、無利子や極端に低金利の社内融資は控除の対象外になる可能性があるため、事前に勤務先へ確認しておくことが重要です。
マイホームを購入する際に住宅ローン控除を受けたい方は、借入先や条件が制度の対象に当てはまるかを必ず確認し、控除を受けられるように計画を立てましょう。
住宅ローン控除の対象となる「住宅の条件」
住宅ローン控除を受けるためには、借入先やローンの種類だけでなく、対象となる「住宅そのもの」が一定の条件を満たしている必要があります。条件は新築住宅の購入、中古住宅の購入、リフォームや増築などの工事によって異なります。ここでは、それぞれのケースで求められる具体的な条件を詳しく解説します。
新築住宅を購入する場合の条件
新築住宅を購入する際に住宅ローン控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
入居開始が遅れると控除の対象外となるため注意が必要です。
床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
投資用や事業用が大半を占める物件は対象外になります。
借入れを行う本人の合計所得金額が3,000万円以下であること
高所得者は制度の対象外です。
登記簿に登録された床面積が50㎡以上であること
小規模な住宅は控除の対象外となります。
住宅ローンの返済期間が10年以上であること
短期ローンでは控除が受けられません。
中古住宅を購入する場合の条件
中古住宅を購入する場合も控除は適用されますが、新築より条件が厳格になります。
特殊な取引は対象外です。
贈与による取得ではないこと
ローンを組んで購入した場合のみ控除が認められます。
耐火建築物の場合は築25年以内であること
耐火建築物以外は築20年以内であること
古すぎる住宅は対象外ですが、耐震基準適合証明を取得すれば対象になるケースもあります。
購入から6ヶ月以内に入居していること
床面積の2分の1以上が居住用であること
合計所得金額が3,000万円以下であること
登記簿に登録された床面積が50㎡以上あること
返済期間が10年以上であること
リフォーム・増築をする場合の条件
リフォームや増築工事でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。
小規模な修繕は対象外です。
店舗兼住宅の場合は住居部分が2分の1以上であること
自ら居住する部分のリフォームであること
工事の内容が大規模リフォーム、省エネ、バリアフリー、耐震改修などであること
工事後6ヶ月以内に入居していること
床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
借入れを行う人の合計所得金額が3,000万円以下であること
登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
返済期間が10年以上であること
『全てがわかる!』
住宅ローンに関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:住宅ローンの全てがわかる!