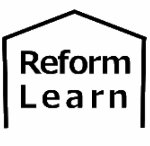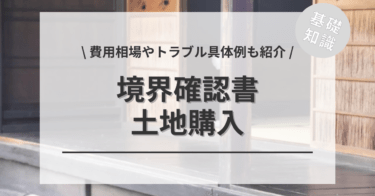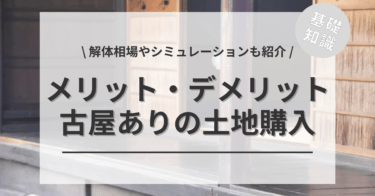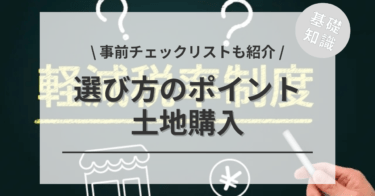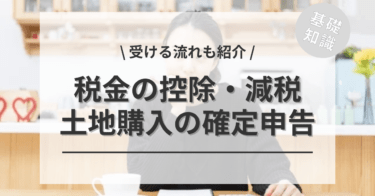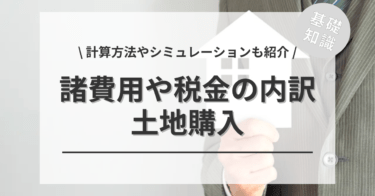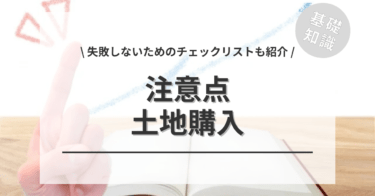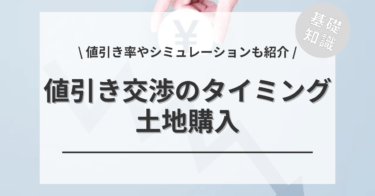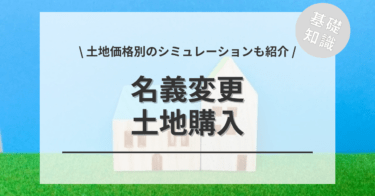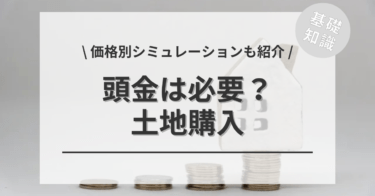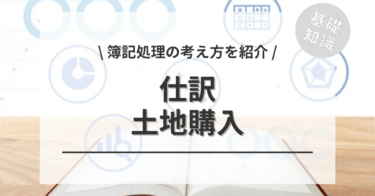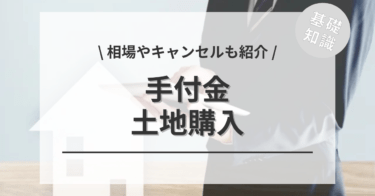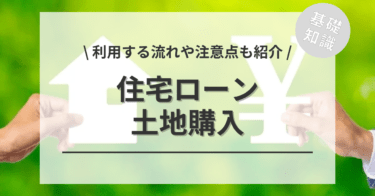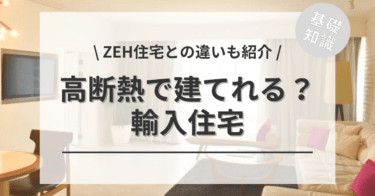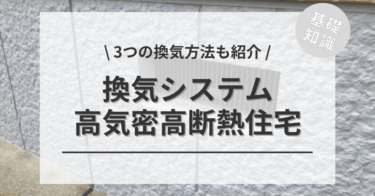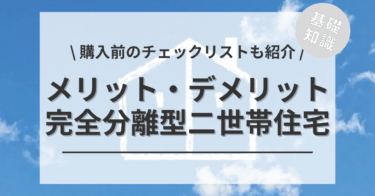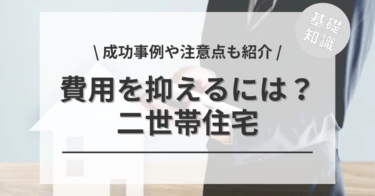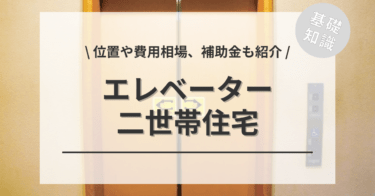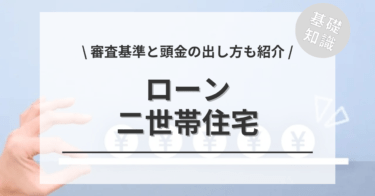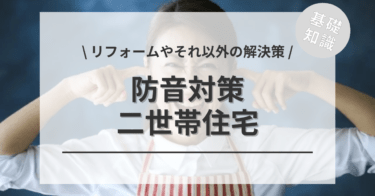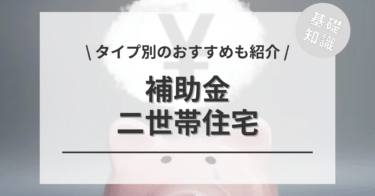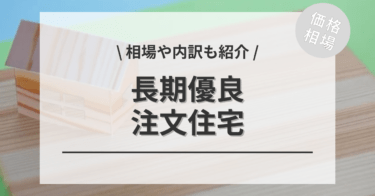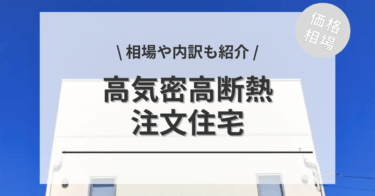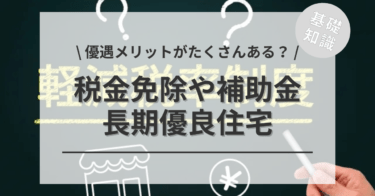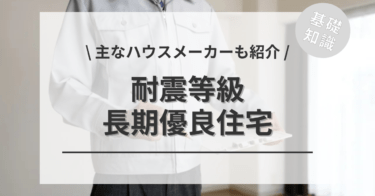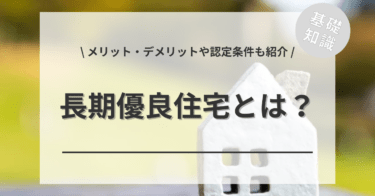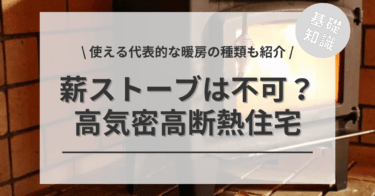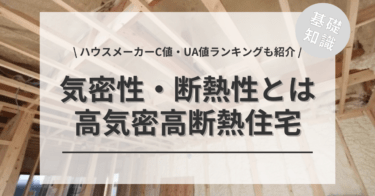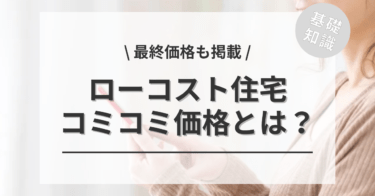土地購入の際に境界確認書は必須?隣人とトラブルにならないための注意点とは?「費用相場」や「具体例」もご紹介
価格や立地だけで決めると、あとで効いてくるのが「境界の曖昧さ」。購入前に測量士立会いで境界を確定し、境界確認書・境界確定図を整えることが、面積・建築計画・資産価値を守る最短ルートです。境界標の設置は隣地同意が原則、塀やフェンスは所有権・維持費の取り決めが肝心。費用は現況測量10〜20万円、境界確定測量30〜60万円、境界標1箇所5,000円〜、紛争時は筆界特定で追加費用が発生します。本稿では、境界確認の手順(資料収集→隣地立会い→測量・標設置→書類作成)、注意点、費用相場、トラブル事例と解決策までを一気に整理。購入後の「想定外コスト」と近隣トラブルを未然に防ぎましょう。